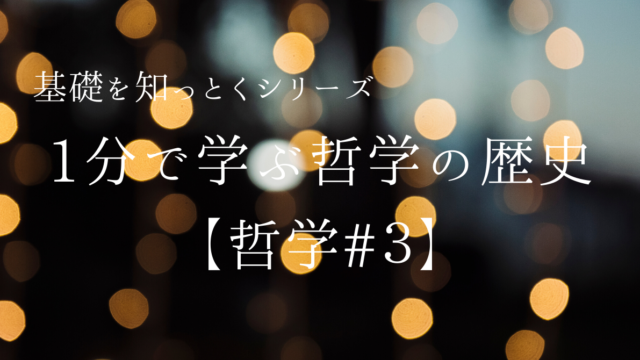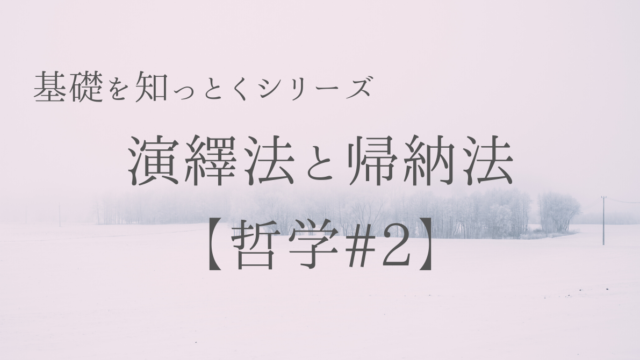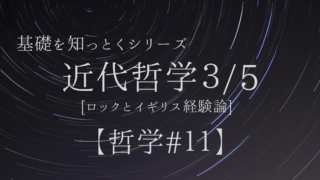近代哲学もあと2回で終わりです。ここまで全体的な近代哲学の流れにはじまり、4つのカタマリのうち、「理性」に注目したデカルトにはじまる大陸合理論、「経験」に注目したロックにはじまるイギリス経験論を見てきました。
今回はのこり2つの社会契約論とドイツ概念論をさらっと見ておきたいと思います。次回が最後になりますが、最後に近代哲学で外せないカントについて少しふれて終わりです。
ちょっと長かったかもしれませんが、もう少しで終わりです。近代哲学は今回と次回の2回で終わりです。
生活に使える哲学をさらっと知っておくことを目的としているので読み飛ばしながら興味があるところだけ進めていきましょう!
それでは近代哲学の4つのカタマリの最後の2つについてみておきましょう!
Contents
■ 社会や国家の成り立ちを考えた社会契約論
社会契約論というのは一言でいうと私たちの社会と国家、市民と国家の関係について考えたテーマであるということが言えます。
中世までは「王が神から命令を受けて作られるものが社会」という普遍的な考えがありました。なので、結局ローマ帝国によるキリスト教の布教などを通じて「神とは何か?」というようなテーマが哲学の世界でも一大テーマとなっていました。
それに対して近代となると文明や科学の発展が大きく影響します。それまで神のワザとした言いようがなかったことが科学的に解明されていきます。そうすることで人間とは何か?というような人にフォーカスされるようになるのが近代という時代といえます。
この時代、イギリスでは名誉革命が起き、フランスではフランス革命が起きるなど大きな社会の変化が巻き起こります。
こういった革命が起きるのはそれまでの中世の絶対的な王(神から命令を受けた存在)による支配とはことなる社会が出来上がってきたということが言えます。それまでただの労働者だった市民が交易をすることで財を成し、新たな階級が生まれます。それまで一切の権利がなかった人々が自分たちの権利を意識しはじめて、自分たちを支配する王の体制に疑問をもつわけです。
そういった社会的な背景に基づいて、そもそも自分たち市民を支配している国家というのはなにか?それは私たちを包み込んでいる社会とどういった関係があるのか?というようなことを考えたのが社会契約論の一連の流れだといえます。
ここでは有名なホッブスとルソーという2人の重要人物をもとにその社会契約論の考え方について簡単に見ていきたいと思います。
殺さない権利を保障しあうのが社会計画と考えたホッブス
ホッブスは清教徒革命が起きたイギリスから逃れてフランスのパリにわたります。そこで彼は国家と社会の成り立ちについて考えます。彼の理論はこうです。
人間同士というのは社会が作られるまでは生きるという欲望をそれぞれが持つだけで殺し合いが起きることが自然状態であると捉えます。そのお互いに殺しあう恐怖から逃れるためにお互いに契約を結ぶことでお互いの生きる権利を侵さないということで社会が成り立つと考えます。その社会をまとめる人が必要ですので、人々がそのそれぞれの生きる権利を公権力にゆだねて国家ができるというのが彼の考えでした。
ホッブスの考えは公権力を擁護するものと捉えられてしまって批判を受けるわけですが、「もし社会がなかったら」という状態を考えてそこから社会と国家の在り方を考えていくアプローチというのはその後の社会契約論に大きく影響を与えたそうです。
革命権や抵抗権を認めたロック
イギリス経験論で登場したロックも社会と国家の関係について考え方を提起しています。
彼は中世のベースとなっていた王権神授説を否定し、社会ができる前の自然状態から社会が出来上がるというホッブスと同じようなアプローチで考えます。
ホッブスは社会が出来上がる前は殺しあう関係があるとしましたが、ロックはもともとそれぞれの人は自由や生命や財産が保護される権利は保証されていると考えました。一方でそういった状態は非常に不安定なので、何か問題が起きたときに「処罰する権利」を公権力が持つことで社会が成り立つと考えたのが彼のアプローチでした。
彼はそういった処罰する権利を国に認める一方で、市民の方も抵抗する権利、革命をする権利があると考えた点が非常に先進的であり、現代の国家に大きな影響を与えています。ロックが偉大であるのはそういった影響力からであり、アメリカの独立宣言やフランス人権宣言などにもその思想は大きな影響を与えたとされています。
市民が国家の運営にかかわるべきと考えたルソー
ルソーはフランスで活動した人物です。彼もホッブスやロックと並んで社会契約論の重要な人物の一人です。
ルソーも社会が作られる前の自然状態から社会の在り方を考えるアプローチで自分の理論を作り上げます。彼によると社会が生まれる前の状態というのは「自己保存の自然な感情と他社への憐み」から成り立っていたと考えます。そういった平和的な状態であったわけですが、文明の発達により色々な権力を主張する人が増え、争いがおこることで不完全な共同体が形成されたと考えます。
この状態を解決するために個人個人が共同体にたいして権力を譲渡する形で社会契約を結んで今の社会と国家という形が作り上げられたと考えました。
彼は独裁政治やファシズムの源流であると否定されることが多いですが、思想としては直接民主制を理想としていた点から批判が正しいかどうかは議論の余地がありそうです。
■ ドイツ概念論:フィヒテ、シェリング、ヘーゲル
社会契約論の次は最後の「ドイツ概念論」です。ドイツ概念論は自然に対し精神を優位とする立場をとり、世界を普遍的理念による体系として構築し、把握しようとする考え方でドイツ理想主義とも言われています。 一言でいうと、精神的なものを世界の根底に実在するものと考えるようなドイツを中心に議論されていたテーマがドイツ概念論と呼ばれています。
このドイツ概念論はカントを始まりとして、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルという3人を大きな一つのくくりにすることが多いです。
このドイツ概念論の大元を作ったカントについては次回、このドイツ概念論と対立的な立場をとるマルクスとセットで扱うことにしておきたいと思いますが、このドイツ概念論の主な登場人物であるフィヒテ、シェリング、ヘーゲルの3人についてここで書いておこうと思います。
それぞれドイツ概念論の同じジャンルですが、フィヒテは主観的な自我の働きに認識の根拠を求めたことから主観的概念論、シェリングは客観的な自然に根拠を求めたので客観的概念論、ヘーゲルはそれぞれを統合した「絶対的概念論」と分けられるのですが、テストを受けるわけではないので、「それぞれアプローチが違う」くらいの認識でもよいと思います。
自我と非我:フィヒテ
フィヒテはドイツ概念論の源流であるカントに見いだされた人物で、自我にスポットを当てた哲学者でした。まず私は私という自我があることが大前提と考えます。自我があるからこそ、自我ではないもの、つまり「非我」という概念が生まれます。まず自我を認識して自我以外のものについては、「自我で認識するからこそ成り立っている」と考えるのが彼の考え方でした。
同一哲学:シェリング
彼はフィヒテの後任として大学で教える人物なのですが、彼は「主観と客観」の一致ということを考えます。彼は主体である自我も客観である非我もすべて一つの宇宙の一部であり、一つの生命であるという壮大な考え方をしています。自然というのは見える精神であり、私たち個人の精神は見えない自然であると考え、すべては世の中の一つのパーツに過ぎないという考え方をします。中世と異なり近代は科学による発展が大きく影響した時代ですが、そういった中でもどちらかというと精神性を大切にした考え方といえるかもしれません。彼のこの考え方は 精神と物質、主観と客観などを二つの独立した実体とはみなさず、絶対的同一者の現象形態と考える立場として「同一哲学」とも呼ばれていてスピノザなども同じ発想だったといわれています。
近代の最大の哲学者:弁証法の大家ヘーゲル
ドイツ概念論の最後はヘーゲルで締めくくりたいと思います。
ヘーゲルは近代の最大の哲学者と言われていて、それまでの近代哲学の様々な議論を一つの体系に集約しようとしたところにその偉大な功績があるとされている人物です。彼は「精神現象学』」という哲学史上最も難解とされる本を書いた人です。
彼は人間の意識は成長するという前提のもと、人が成長すると見えている世界もそれに応じて変わってみえるようになると考えます。
彼は歴史も同じだと説きます。古代ギリシャ時代は個人と共同体の意識はわかれていません。やがて共同体への信頼が失われることで個人の意識にスポットが当たり個人と共同体で争いがおきます。そのうえで個人と共同体がお互いを認め合うことで社会が作られると考えました。
このように個人の意識も歴史も、その絶対精神が自身を目覚めさせていくプロセスであるとかんがえました。
ヘーゲルといえば弁償法と思いだす人も多いかもしれません。アンチテーゼという言葉を知っている人も多いかもしれませんが、これは古代ギリシャから続く弁証法の考え方に出てくる言葉の一つです。
まず相手の主張を認めること(テーゼ)からはじまり、次にそれと矛盾する立場を相手の前提から導き出すことをアンチテーゼと呼びます。そして最後にその2つの対立する立場を総合するより高い次元の立場を作ることをジンテーゼと呼び、この一連の論理的な考え方を「弁証法」と呼んでいます。
例えば夫婦関係について考えてみます。私は自律した人間として生きていくために妻を見つけて所帯を持ちます。ところが彼は自律しているようでありながら実は妻にかなり依存していることに気づきます。そこで彼は自分一人で生きるわけでもなく、妻に依存するわけでもなく、第三の立場を考えて自立しながら妻と夫婦関係をもつという第三の立場を目指すようになります。このように、1つ目の立場、2つ目の立場それぞれどちらがいいというわけではなく、それぞれを超越する第三の立場を考えていくことを弁証法的なアプローチであるということができます。
■ 最後に:マルクス
以上、国家と社会の関係について考えるという社会契約論と、ドイツで主に議論されていたドイツ概念論について簡単に触れておきました。特にドイツ概念論は少し難しいのでわかりづらい説明だったかもしれません。申し訳ありません。
ドイツ概念論の最後に触れたヘーゲルに関係する人物を最後に1人紹介しておきたいと思います。それはマルクスです。マルクスと聞くと共産主義を思い出す方も多いかもしれません。
マルクスは労働者階級(プロレタリアート)が資本家を倒して自身の手になかった工場などを所有することで共同体を作るという考えを作り上げた人物です。彼は資本家と労働者という階級闘争を乗り越えて「共産主義への移行」を唱えました。
そんなマルクスはドイツ概念論のところで出てきたヘーゲルを真っ向から否定した人物でもあります。自我や理性、精神といった観念を重視するドイツ概念論に対して、そういったものは精神的な話であり、より物質的で現実的な基盤を重視する立場をとりました。
彼の考えからすると、資本主義社会という、いわば「資本家VS労働者」という構図は人類の発展の途中段階であり、階級のない社会になるには社会主義を通じて最後は共産主義にたどり着くものであるということになります。これがいいか悪いかは別にして、ドイツ概念論を否定したマルクスの立場があったということだけでは覚えておいても良いかもしれません。
以上、今回は社会契約論とドイツ概念論、ドイツ概念論を否定したマルクスについて触れました。
近代哲学は次回が最後の5回目になりますが、ドイツ概念論の源流であるカントについて触れたいと思っています。