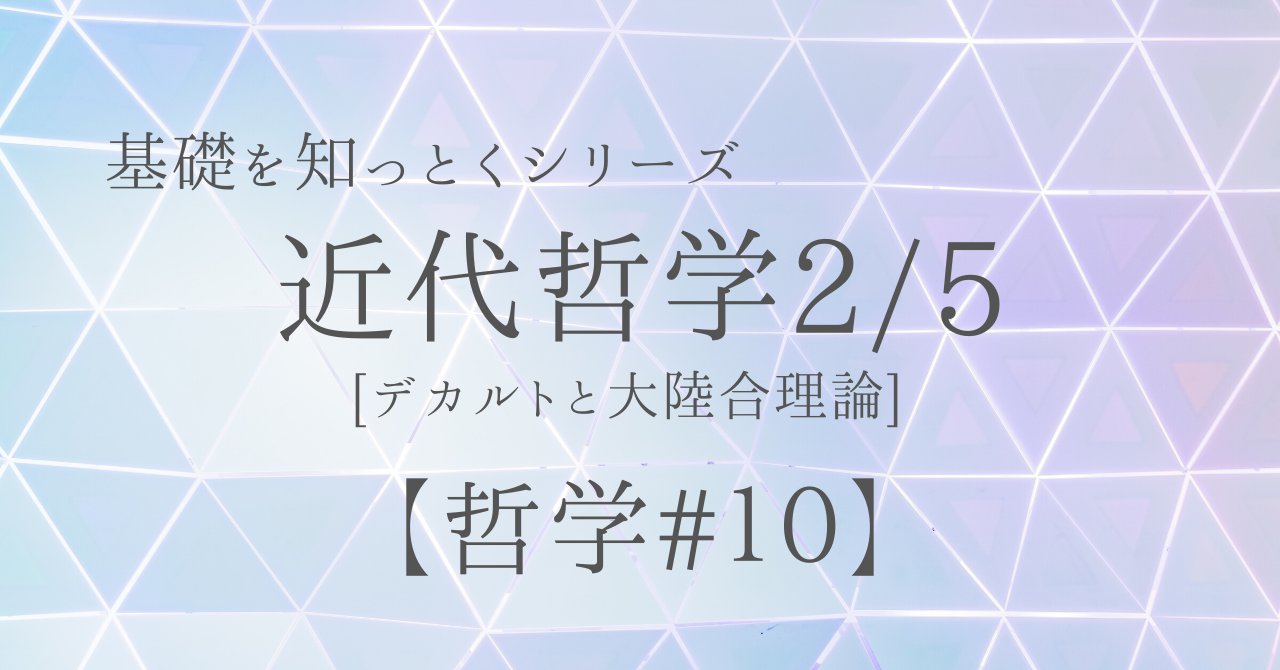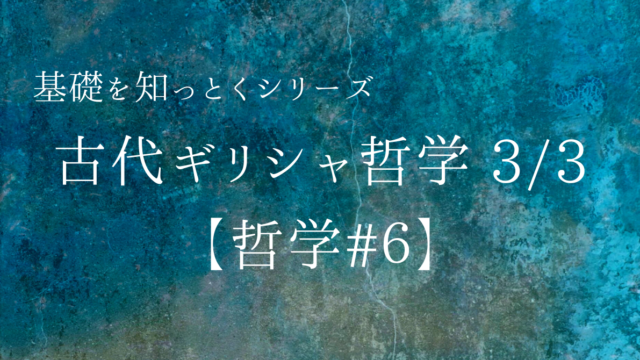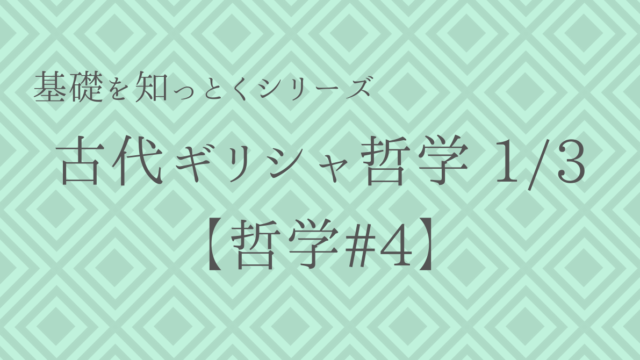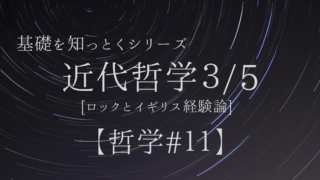ここまで古代ギリシャ哲学から中世哲学を経て前回は近代哲学の大まかな流れと登場人物について書いてきました。
近代哲学は4つの大きなカタマリで理解しようと思っています。その4つは大陸合理論、イギリス経験論、ドイツ概念論、社会契約論というそれぞれ異なった哲学のテーマを論じている流れなので、その中で登場人物について少しずつふれていこうと思っています。
それでは今回は最初のカタマリとして、大陸合理論についてその代表的な存在であるデカルトを中心に説明していきたいと思います。
Contents
■ 大陸合理論とはどういったジャンルか
前回の記事で近代哲学を理解するうえで4つのカタマリで理解するということを書きましたが、大陸合理論はどういった理論といえるでしょうか。
一言でいうと、合理的な理性を人間が持っていて、その合理的な人間が世界を解釈しようとするヨーロッパの哲学ということができます。
その代表的な3人がデカルト、スピノザ、ライプニッツなのですが、その3人より少し前に登場したフランシスコ・ベーコンを加えて4人を覚えておけば大陸合理論はだいたいつかめていると思ってよいと思います。
■ フランシスコ・ベーコンはとにかく実験を重視

近代といえば1500年から1800年頃の話で科学技術がとても発達した時期でした。コペルニクスやニュートン、ガリレオなどそうそうたる人たちが活躍した時代でもありました。
そんな時代に哲学についてもとにかく実験を重視したのがフランシスコ・ベーコンでした。彼は近代哲学の先駆けといわれています。
モノゴトを考える上で2つの考え方があるということは哲学シリーズの2回目の記事で説明しました(こちら)。演繹法(ある絶対的な原則から個別の事象を導く考え方)と帰納法(個別の事象から結論を出している考え方)があるわけですが、フランシスコ・ベーコンは帰納法でとにかく実験と観察を繰り返して一般的な理論や法則を導くことを重視した人でした。
彼は先入観をもってはいけないということを主張していて、先入観や偏見をもってしまう4つの要因をイドラと呼びました。1つ目は種族のイドラといって人間はもともと錯覚に陥りやすい性質があるということ。2つ目は洞窟のイドラといって人間は性格に偏りがあるということ。3つ目は市場のイドラといって人間が交流することで言葉を交わしますがそこには錯覚があるということ。4つ目は劇場のイドラといって従来の伝統や権威に人間は盲目になってしまうということ。この4つのイドラがあることで人間は先入観や偏見をもってしまうという彼の指摘は今私たちが聞いてもかなり鋭いと感じます。
■ デカルト=近代哲学の父

近代哲学で一番外せない人物といえばデカルトといえます。彼のあとに続いたスピノザとライプニッツをあわせて大陸合理論というくくりで語られることが多いですが、まずはデカルトについてどういった人だったかについて簡単に書いていきたいと思います。
デカルトはとにかく徹底的にモノゴトを疑うことを大切にした人でした。彼はフランス名門の学校でスコラ哲学を学びましたが意見がみんなバラバラであることに疑問を抱き、旅に出ます。すると、ある国では常識としていることが他の国では非常識だったり、ある国では当たりまえの習慣が他の国ではまったく行われていないということに気づき、自分の考えもある種の先入観のもとに出来上がっているのだと感じるようになります。
彼は徹底して疑うことを「方法的懐疑」といって、とにかく徹底して疑うべきものを疑っていけば、いずれ疑うことができない真理にたどり着けると考えたようです。
彼はとにかく色々なことを疑っていくのですがキリがありません。どこに確実な存在はないように思えてきます。
ところが、色々なことを疑っている間も「疑い続けている私」という存在は存在していることに気づき、有名な「われ思うゆえにわれあり」という言葉を残します。そして「私」という自分に目を向けて、「確実に存在している主体としての私」と「私をとりまく客観」というモノゴトの見方にたどり着きます。
そんなデカルトは「二元論」を唱えます。彼はこの世は「精神と物質」という2つのものでできていると考えました。色々とものごとを疑っている考えを「精神」と名付けて、その精神がとらえる世界を「物質」と呼びました。これはどういうことかというと、精神は人間の思考や考えが本質にありますが、物質というのは形を自在に変わるものというとらえ方をした考えです。
彼はこの精神と物質に「神」を加えた3つが世界の三大構成要素と定義づけました。人間は有限な素材ですが、無限という観念を生まれながらにして持っているので、その観念を授けたものがいるはずであり、それが「神」であるというのが彼の理論でした。
また彼は数学者でもあり科学者だったことから常にモノゴトを疑い真理を探す活動をしていました。彼はそういった研究を通じで自然や党物、人間の肉体は「機械」であるというとらえ方をしました。この考え方は「機械論」と呼ばれています。ブリタニカ国際大百科事典によると「自然や社会や生物を扱うときに内的目的や霊魂を排除してどこまでも物質的な諸要素の集合とその運動として決定論的に取り扱う態度。すなわち有機体をモデルにするのではなく機械をモデルとして対象を考察する態度のことである」と説明されています。
以上がデカルトのざっくりとした説明になります。詳しく知りたい方は専門書がたくさん出ているので読んでいたただくとして、ここでは中世哲学でだいぶ異なっていて、かなりサイエンスに近い考え方に基づいているということがわかると思います。デカルトの登場により近代哲学はさらに発展していきますが、彼の流れを継いだのがスピノザとライプニッツでした。
■ スピノザ:この世のすべてが神

スピノザはユダヤ教やキリスト教から破門とされ宗教に対する疑問を抱きます。彼は「喜び」を感じている時の方が神を感じることができると考えた哲学者でした。かれの思想は「汎神論」と解説されています。この考え方は「この世の中すべてが神」「神は無限である」という考え方をさします。無限ということは限界がないということですが、神が無限であれば線引きはできないのですべてが神に内包されるということです。これがスピノザの神に対する考え方でした。
彼はデカルトはこの世の中は精神と物質と神という3つの本質でできているという主張を批判します。彼は精神と物質は神の多様な在り方の一つという考え方の方が良いということを主張し、神が無限であり、この世の中のすべてが神であるのだという自分の主張を強めます。精神と物質を別々に考える必要はなくてすべて神に内包されるのだから並行して存在してよいという意味でこのような考え方は「心身並行論」と呼ばれます。
神と神が作り出した世界といように考えるユダヤ教やキリスト教とは全然異なる考え方をすることから彼は異端と捉えられてしまいます。
■ ライプニッツ:世界は最小単位の物質を神が設計した
ライプニッツは世界がこれ以上分割できない最小単位を「モナド(単子)」となずけました。とにかく分解しまくっていくとすべてのものはモナドという最小の単位に分解できると考えたのです。
神があらかじめモナドの働き方を設計した私たち人間や、犬、動植物を作り上げたというのが彼の理論でした。彼の言うモナドというのは物質ではなくてあくまで最小の「単位」という考え方でした。この最小の単位に勢いが加わると個体としての感じられると説き、このような最小単位を作り上げられるのは神だけであり、神がすべてを計画したという彼の考えを「予定調和説」と呼んでいます。
■ 最後に
以上で近代哲学の最初のカタマリである大陸合理論について終わりです。あとの3つであるイギリス経験論、ドイツ概念論、社会契約論はそれぞれ次回触れていこうと思います。
この大陸合理論の一連の登場人物であるデカルト、スピノザ、ライプニッツはいずれも人間には合理的な理性があって、その合理的な人間が世界を解釈しようとする考え方を代表している哲学者たちだといえます。
誰も神の存在を疑ってはいませんが、アプローチとしては科学的であり理論的であるといえます。近代のように科学が発達していくと、果たしてこれは哲学なのか、科学なのか数学なのか境界線がわからなくなってきますが、「そもそもの前提を疑って考えること」自体が哲学だとしたらオーバーラップして当然ですね。
それではまた次回。